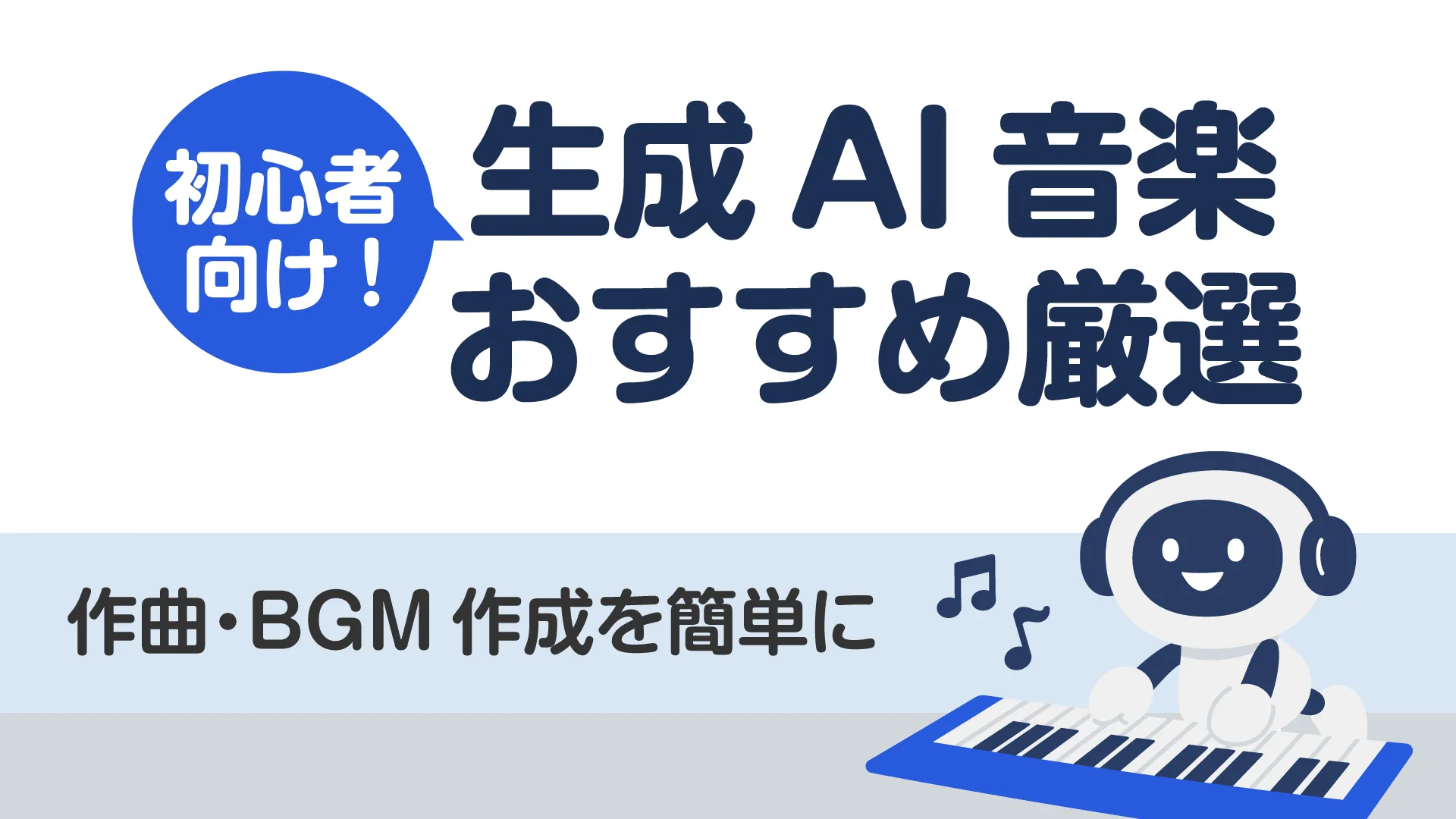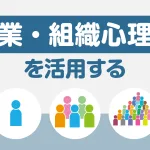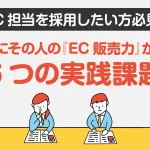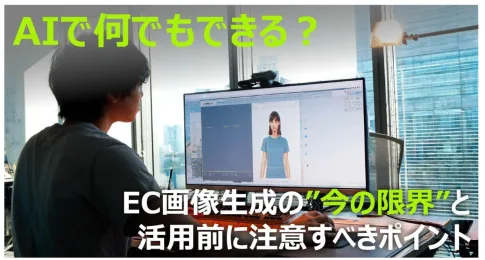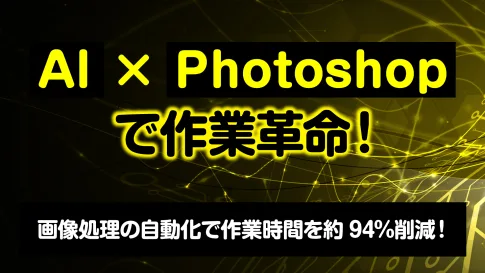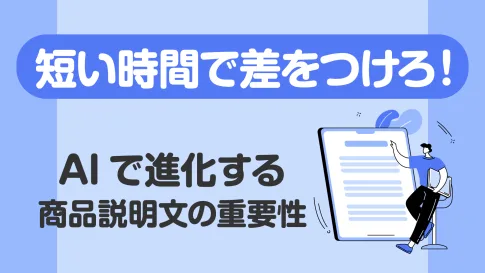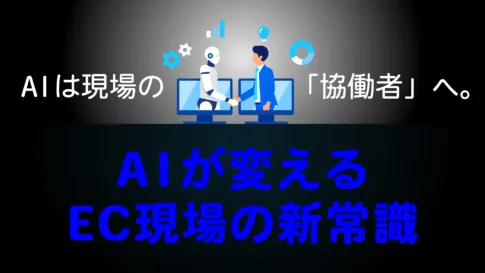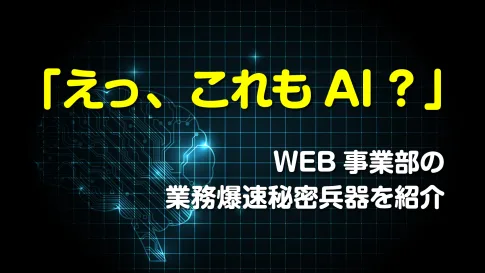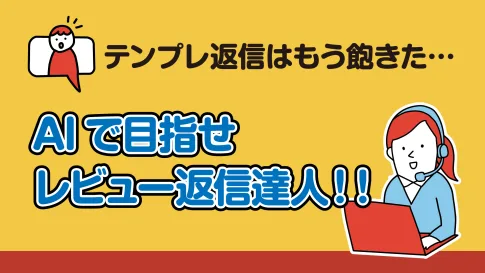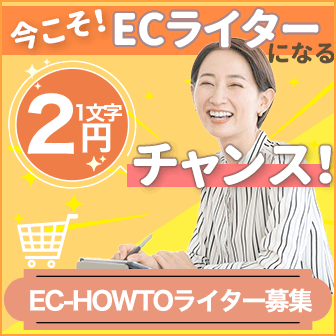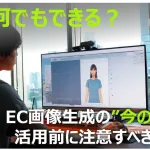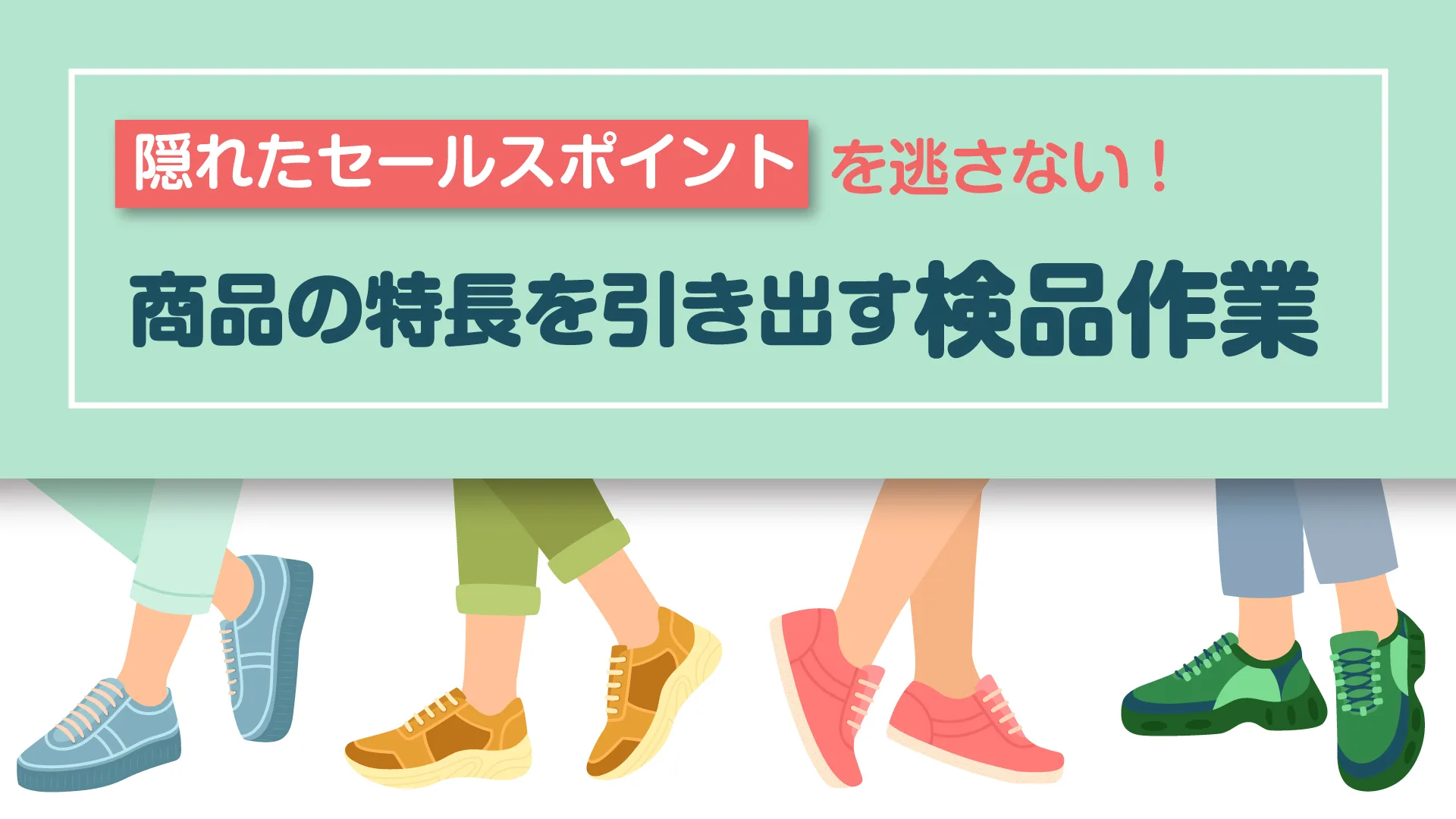「動画のBGM制作に時間がかかっている…」
「音楽の知識がないから作曲は無理…」
そんな悩みを抱えていませんか?本記事では、音楽の専門知識がなくても手軽に高品質なBGMを作成できる、おすすめの生成AI音楽ツールを厳選してご紹介します。無料から有料まで、あなたのニーズに合ったツールがきっと見つかります。AIを活用して、効率的な音楽制作を実現しましょう。
目次
1. 生成AI音楽とは?基礎知識と注目される背景
音楽生成AIは、音楽制作の知識がない方でも、簡単にクオリティの高い楽曲やBGM生成を可能にします。本章では、その基礎知識から注目される背景、メリット・デメリットまでを網羅的にご紹介します。
1.1. 生成AI音楽とは何か
生成AI音楽とは、人工知能(AI)が学習データに基づいて自動で作曲や編曲を行う技術を用いて生成された音楽のことを指します。従来の作曲方法では、作曲家が楽器を演奏したり、楽譜を作成したりする必要がありました。
しかし、生成AI音楽では、AIが学習した膨大な音楽データをもとに、新たな音楽を生成します。例えば、あるAIはクラシック音楽のパターンを学習し、別のAIは現代ポップの構造を理解することで、それぞれのスタイルに合った音楽を生成することが可能です。
これにより、音楽制作の知識がない人でも、AI作曲によって手軽にオリジナルの楽曲を手に入れることができるようになります。
1.2. 音楽生成AIが注目される背景
音楽生成AIが注目される背景には、大きく分けて3つの要因が存在します。1つ目は、動画コンテンツ市場の拡大です。YouTubeやTikTokなどのプラットフォームの普及により、個人や企業が制作する動画コンテンツの量が飛躍的に増加しました。
それに伴い、BGM生成の需要も高まっています。2つ目は、人手不足の問題です。動画編集者やコンテンツクリエイターは常に、著作権フリーで高品質なBGMを探していますが、その作業には時間がかかります。3つ目は、AI技術の進化です。近年のAI技術の進歩により、高品質で多様な音楽を生成することが可能になり、多くのクリエイターがAI作曲に注目しています。
1.3. 音楽生成AIのメリット・デメリット
音楽生成AIには、多くのメリットがある一方、デメリットも存在します。メリットとしては、制作時間の短縮、コスト削減、アイデアの創出などが挙げられます。AIは人間よりも高速に音楽を生成できるため、制作時間を大幅に短縮できます。
また、有料の作曲家に依頼するよりも、無料または低コストで音楽を入手できる場合が多いです。さらに、AIは既存の音楽にはない斬新なアイデアを提供してくれる可能性もあります。
しかし、デメリットとして、著作権の問題、表現の限界、オリジナリティの欠如などが挙げられます。
AIが生成した音楽の著作権は誰に帰属するのか、商用利用は可能なのかなど法的な問題があります。また、AIは学習データに基づいて音楽を生成するため、既存の音楽のパターンを踏襲することが多く、真に新しい音楽を生み出すことは難しいという側面もあります。
2. 音楽生成AIを選ぶ際の重要ポイント5選
数ある音楽生成AIツールから、最適なものを選ぶためには、いくつかの重要なポイントがあります。ここでは、料金体系、音楽のクオリティ、著作権の取り扱い、使いやすさ、商用利用の可否という5つのポイントに焦点を当てて解説していきます。
2.1. 料金体系(無料 vs 有料)(250文字)
音楽生成AIの料金体系は、大きく分けて無料版と有料版があります。無料版は、基本的な機能が利用できるものの、生成できる楽曲数や音質に制限がある場合があります。例えば、生成できる楽曲の長さが1分までだったり、利用できる楽器の種類が限られていたりすることがあります。
一方、有料版は、より高機能なオプションが利用でき、生成できる楽曲数や音質に制限がない場合が多いです。有料版の中には月額980円のようなサブスクリプションモデルや、1曲あたり500円のような従量課金モデルなど料金体系は様々です。そのため、自身の利用頻度や予算に合わせて、最適な料金体系を選ぶことが重要です。
2.2. 生成される音楽のクオリティ
音楽生成AIを選ぶ上で、生成される音楽のクオリティは非常に重要なポイントです。AI作曲の技術は日々進化していますが、ツールによっては、生成される音楽の質に大きな差があります。無料ツールの場合、クオリティが低い音楽しか生成できないこともあります。
有料ツールであれば、高音質でプロの作曲家が作ったようなクオリティの高い音楽を生成できるものもあります。音楽のクオリティを評価するためには、実際にツールを試してみたり、ユーザーレビューを参考にしたりすることが有効です。
2.3. 著作権の取り扱い
音楽生成AIを利用する際には、著作権の取り扱いについて十分に注意する必要があります。AI作曲によって生成された音楽の著作権は、誰に帰属するのか、商用利用は可能なのかなど、ツールによってルールが異なります。
無料ツールの中には、生成された音楽の著作権がツール提供者に帰属するものや、商用利用が禁止されているものもあります。有料ツールであれば、生成された音楽の著作権が利用者に帰属し、商用利用も可能な場合が多いですが、利用規約をよく確認する必要があります。
2.4. 使いやすさ(初心者向けか)
音楽生成AIを選ぶ際には、使いやすさも考慮しましょう。特に、音楽の専門知識がない初心者の方は、直感的に操作できるツールを選ぶことが大切です。AI作曲ツールの中には、プラグインのような専門知識が必要なものから、Webサービスやアプリのように簡単に使えるものまで、様々な種類があります。例えば、初心者向けのWebサービスであれば、簡単な質問に答えるだけでAIが、自動的にBGM生成してくれるものがあります。
2.5. 商用利用の可否
音楽生成AIを選ぶ上で、商用利用の可否は非常に重要なポイントです。生成された音楽をYouTube動画やアプリのBGMとして利用したり、Webサービスで販売したりする場合には、商用利用が許可されているツールを選ぶ必要があります。
無料ツールの中には、商用利用が禁止されているものや、クレジット表記が必要なものがあります。有料ツールであれば、商用利用が可能な場合が多いですが、利用規約をよく確認し、著作権に関する条項を理解しておく必要があります。
3. 【無料あり】おすすめ音楽生成AIツール5選
ここでは、無料で試せるものから、本格的なAI作曲が可能な有料ツールまで、おすすめの音楽生成AIツールを5選ご紹介します。それぞれのツールの特徴、料金、使いやすさ、クオリティ、商用利用の可否などを比較し、あなたに最適なツールを見つけましょう。
- 3.1. Mubert
- 3.2. Amper Music
- 3.3. Ecrett Music
- 3.4. SOUNDRAW
- 3.5. Boomy
3.1. Mubert (英語対応)
MubertはAIが自動でBGM生成してくれるWebサービスです。音楽生成AIの知識がない初心者でも簡単に、クオリティの高い音楽を作成できます。Mubertの最大の特徴は、豊富なジャンルの音楽を生成できることです。エレクトロニック、アンビエント、ヒップホップなど、様々なジャンルの音楽に対応しています。
また、生成された音楽は商用利用も可能です。Mubertは、無料プランと有料プランがあります。無料プランでは、生成できる音楽の長さに制限がありますが、有料プランでは、より高音質な音楽を生成できます。
3.2. Amper Music (日本語対応可)
Amper Musicは、AIが作曲を支援してくれるWebサービスです。AI作曲の経験がない初心者でも、簡単にオリジナル楽曲を作成できます。Amper Musicの最大の特徴は、豊富な楽器の種類を選択できることです。ピアノ、ギター、ドラムなど、様々な楽器を選択し、楽曲をカスタマイズできます。また、Amper Musicは、商用利用も可能です。アプリやWebサービスのBGMとして利用できます。Amper Musicは、有料プランのみです。
3.3. Ecrett Music (英語対応)
Ecrett Musicは、AIがBGM生成してくれるWebサービスです。音楽生成AIの知識がない初心者でも、簡単な操作でクオリティの高い音楽を作成できます。
Ecrett Musicの最大の特徴は、ロイヤリティフリーの音楽を提供していることです。生成された音楽は、著作権フリーで商用利用も可能です。Ecrett Musicは、有料プランのみです。
3.4. SOUNDRAW (日本語対応)
SOUNDRAWは、AIがBGM生成してくれるWebサービスです。AI作曲の経験がない初心者でも、直感的な操作で音楽をカスタマイズできます。SOUNDRAWの最大の特徴は、豊富なテンプレートが用意されていることです。
様々なジャンルのテンプレートを選択し、自分の好みに合わせて音楽をカスタマイズできます。また、SOUNDRAWは、商用利用も可能です。WebサービスやアプリのBGMとして利用できます。SOUNDRAWは、有料プランのみです。
3.5. Boomy (英語対応)
BoomyはAIが作曲を支援してくれるWebサービスです。AI作曲の経験がない初心者でも簡単に、オリジナル楽曲を作成できます。Boomyの最大の特徴は、作成した楽曲を配信できることです。
Boomyで作成した楽曲をSpotifyやApple Musicなどの音楽配信サービスで配信し、収益を得ることができます。また、Boomyは、商用利用も可能です。アプリやWebサービスのBGMとして利用できます。Boomyは、無料プランと有料プランがあります。
4. 音楽生成AIを活用する際の注意点
音楽生成AIは非常に便利なツールですが、利用する際にはいくつかの注意点があります。ここでは、著作権侵害のリスク、AIへの依存、契約内容の確認という3つの点について解説します。
4.1. 著作権侵害のリスクを避ける方法
音楽生成AIを活用する上で、最も注意すべき点は、著作権侵害のリスクです。AIが生成した音楽が既存の楽曲と酷似している場合、著作権侵害に当たる可能性があります。そのため、音楽生成AIを利用する際には、類似楽曲のチェックツールなどを活用し、著作権侵害のリスクを回避する必要があります。
また、AIの利用規約をよく読み、著作権に関する条項を理解しておくことも重要です。
4.2. AIに頼りすぎない、オリジナリティの追求
音楽生成AIは非常に便利なツールですが、AIに頼りすぎると、オリジナリティのない音楽になってしまう可能性があります。AIはあくまでツールであり、人間の創造性を代替するものではありません。
AIが生成した音楽をそのまま利用するのではなく、人間の手でアレンジを加えたり、楽器を演奏したりすることで、オリジナリティ豊かな音楽を制作するように心がけましょう。AI作曲と人間の創造性の融合が、新しい音楽を生み出す鍵となります。
4.3. 契約内容の確認と利用規約の遵守
音楽生成AIを利用する際には、各ツールの契約内容や利用規約をしっかりと確認し、遵守することが大切です。無料ツールの中には、商用利用が禁止されているものや、著作権がツール提供者に帰属するものがあります。
有料ツールであれば、商用利用が可能な場合が多いですが、利用規約をよく確認し、著作権に関する条項を理解しておく必要があります。契約内容や利用規約に違反すると、法的なトラブルに発展する可能性があるので、注意が必要です。
5. 音楽生成AIで手軽に高品質なBGM制作を
この記事では、音楽生成AIの基本知識から、ツールの選び方、おすすめのツール、活用時の注意点まで幅広く解説しました。音楽生成AIを活用することで、誰でも手軽にクオリティの高いBGM生成が可能です。ぜひこの記事を参考に、あなたにぴったりのAI作曲ツールを見つけて、効率的な音楽制作を実現してください。
現場で役立つプレゼント付き!最新ECノウハウで実践力が身につく! ECハウツー7日間 無料メルマガ講座に登録する